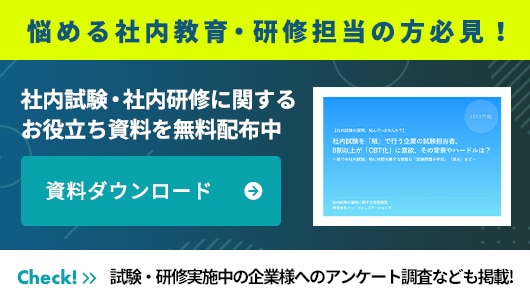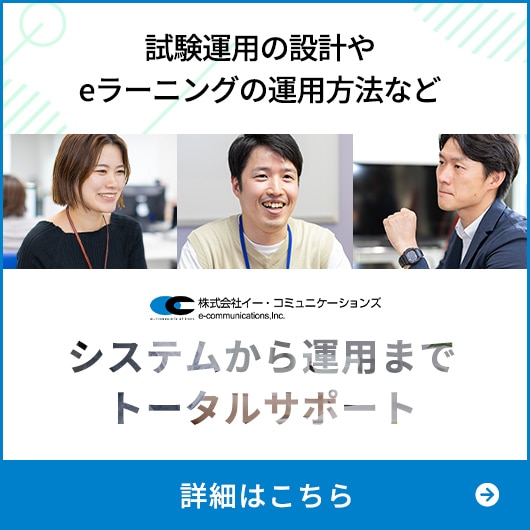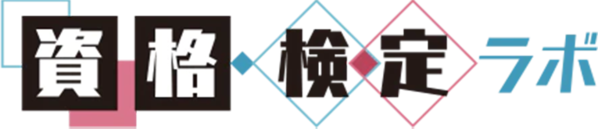eラーニング研修のメリット・デメリット!導入事例もご紹介
社内研修の形式はさまざまですが、そのひとつに「eラーニング」を活用する方法があります。この記事では、研修にeラーニングを検討・導入する場合に必要な情報をまとめました。
eラーニングが活用できる研修内容、導入のメリット・デメリット、導入までのステップなどをご紹介しますので、eラーニング研修の実施をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次[非表示]
- 1.eラーニング研修とは
- 2.eラーニング研修のメリット
- 2.1.いつでもどこでも受講できる
- 2.2.対面研修と比べてコストがかからない
- 2.3.講師の指導力に左右されない
- 2.4.学習内容の修正・更新が容易にできる
- 2.5.全社員の学習管理が容易にできる
- 3.eラーニング研修のデメリット
- 3.1.リアルタイムでの対話が難しい
- 3.2.モチベーションの維持が難しい
- 3.3.実技の習得は難しい
- 4.eラーニング研修の内容一覧
- 4.1.コンプライアンス・ハラスメント研修
- 4.2.新人研修(ビジネスマナーなど)
- 4.3.階層別研修(中堅社員・管理職)
- 4.4.ビジョン研修(企業理念・会社方針など)
- 4.5.専門知識に関する研修
- 4.6.語学研修
- 4.7.接客・クレーム対応など
- 5.eラーニング研修の導入前に考えるべきこと
- 5.1.①研修全体のゴールと設計
- 5.2.②eラーニングで行いたい内容・条件
- 6.eラーニング研修を導入する4つのステップ
- 6.1.ステップ1 内容・対象・時期・担当者を決定
- 6.2.ステップ2 システム検討・導入
- 6.3.ステップ3 実施
- 6.4.ステップ4 フォローアップ
- 7.eラーニング研修を成功させるためのポイント
- 8.ラーニング研修の導入事例
- 8.1.事例1.不動産系企業様
- 8.2.事例2.IT系企業様
- 8.3.事例3.マーケティング系企業様
- 9.eラーニング研修にはSAKU-SAKU Testingをご活用ください
eラーニング研修とは

eラーニング研修は、eラーニングを取り入れた研修方法です。eラーニングの導入には、LMS(Learning Management System:学習管理システム)というプラットフォームを利用する例が一般的です。
もともと、企業研修は対面研修が主流でした。しかし、企業の規模が大きくなるにつれ、下記のような課題が浮き彫りになってきました。
- 場所や時間の確保が難しい
- 教材の作成に追いつかない
- 誰がどの研修を受けているかを把握しきれない
このような課題を解決する手段として、多くの企業がeラーニング研修を取り入れ始めています。
なお、eラーニングとはPC、スマートフォン、タブレットなどを使用した学習方法をいいます。企業の成長に寄与する効果的な研修手段として広く利用されています。
eラーニングについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
「eラーニングとは?活用例やメリット・デメリットをわかりやすく解説」
eラーニング研修のメリット

次に、eラーニングで研修を行うメリットについて説明していきます。
いつでもどこでも受講できる
受講者側はPCだけではなく、スマートフォン、タブレットからアクセスできます。通勤中のすきま時間など、時間や場所に縛られず受講できるのがメリットです。
主催者側としても時間の確保や、会場手配や複雑な手続きが不要で、移動の手間もかかりません。また人数分のPCがない部署でも同じ研修を実施することができます。
対面研修と比べてコストがかからない
eラーニング研修は初期の導入費用がかかるものの、対面研修と比べてコスト削減が見込めます。一度導入してしまえば、会場の手配などの手間が削減でき、会場のレンタル、移動費、印刷物の制作費用も不要です。受講者は個々のデバイスからアクセスでき、交通費などの経費を削減できます。
これにより、質の高い教育プログラムを提供し、同時にコストを軽減できるため、多くの組織がeラーニングを採用しています。
講師の指導力に左右されない
対面研修のように同じ内容の研修を複数の講師が担当する場合、講師の力量によって受講者のスキル・知識に差が生じることがあります。
eラーニング研修では、全社員に同じ学習教材を提供できるため、そのようなことがありません。
すべての従業員が同じ内容を受けることで、組織全体で共通の知識を身に付けたり、スキルを均一化したりできます。
学習内容の修正・更新が容易にできる
eラーニングを活用すれば、学習コンテンツの修正と更新が容易にできます。主催者は常に最新の情報や学習してほしいトレンドに即したコンテンツを提供することが可能です。
受講者側も、最新の情報に基づいたコンテンツを学べるため、専門知識の習得やスキルの向上に役立てられます。
全社員の学習管理が容易にできる
企業規模が拡大するにつれ、全社員の学習進捗や成績を管理することは難しくなります。一方、eラーニングはシステム上で学習データを収集・管理するため、学習管理が容易にできます。
以下は、eラーニングシステムで利用できる学習管理機能の一例です。
|
・未受講の研修に関して通知やリマインダーを行う
・成績が一定の基準に達していない受講者に再受講を促す
|
機能を効果的に利用することで、全従業員のスキル向上を確保することができます。
eラーニング研修のデメリット

eラーニング研修にはデメリットもあるため、導入する場合は対策が必要です。
デメリットについてもみていきましょう 。
リアルタイムでの対話が難しい
eラーニング研修の中には、リアルタイムの対話やディスカッションが不足するという課題があります。
eラーニング研修での動画教材は事前に録画された動画を配信することが多く、その場合は講師に直接質問したり、ほかの受講者と話し合ったりすることができません。
受講者間での直接のコミュニケーションを制限することもあり、議論や対話の質が低下する可能性があります。
この課題を解決するには、eラーニングと対面研修を組み合わせることが一つの解決策となります。ディスカッションや対話が重要な研修の場合は、対面研修で受講者が直接質問し、意見交換できる機会を作ります。これにより、eラーニングの柔軟性と効率性を保ちつつ、eラーニング研修だけでは補えない部分を解消することができます。
モチベーションの維持が難しい
eラーニング研修には、受講者のモチベーション維持が難しいという課題があります。オンライン学習は個人が自己責任で進めるため、対面研修のように教室内での学習仲間との刺激が欠け、集合研修と比べモチベーションの低下が起こりやすいのです。
この課題を解決するには、主催者側が学習の進捗に関するメール通知や課題提出のリマインダーなどを自動的に送信する「メール配信機能」を利用することが有効です。
また、報酬やバッジなどの受講者への認定制度を導入することもモチベーション向上に役立ちます。受講者同士のコミュニケーションを促進するためのチャットルームの設置も有効です。
受講者のモチベーションを維持するためには、受講率を向上させるための機能が備わっているeラーニングシステムを選ぶことも重要です。
実技の習得は難しい
eラーニング研修は実技の習得に関しては一定の制約が存在します。特に、実技のスキルやロールプレイングが必要となる分野では、オンライン学習だけでは習得するのは難しい場合があります。
この課題を解決するためには、動画コンテンツを使用することがおすすめです。
実技の手順や技術を視覚的に理解できるように、わかりやすい動画コースが提供されているプラットフォームを利用しましょう。また、対面研修との併用も検討しましょう。講師から直接指導を受けることで、スキルや技術の習得ができます。
eラーニング研修の内容一覧

eラーニングは、さまざまな研修に活用することができます。具体的には次の例があります。
- コンプライアンス・ハラスメント研修
- ビジネスマナーなど新人研修
中堅社員・管理職など階層別研修
企業理念・会社方針など
業務上必要な専門知識
語学研修
接客・クレーム対応など
ひとつずつみていきましょう。
コンプライアンス・ハラスメント研修
コンプライアンス・ハラスメント研修では、すべての社員が内容を理解して行動に反映できる状態にする必要があります。全社員を対象とした集団研修を行う企業も多いですが、企業規模によってはスケジュール調整や会場の準備に手間がかかります。そこで、各個人が繰り返し学べるeラーニングが学習に適しています。
また、コンプライアンスやハラスメントは企業によって学ぶべき内容の差が少ないため、eラーニングでは既製のコンテンツが数多く用意されています。自社でコンテンツを作成しなくても必要な範囲の多くを既製のコンテンツでカバーでき、少ない負担で学習が可能です。
ただし階層によって注意すべきポイントが違うため、研修内容が管理者と一般社員とで変わります。その際もeラーニングなら配信内容を変えるだけで対応できるので、講師を招いて階層別の内容の講義を何度も行う必要がありません。
イー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」では、コンプライアンスやハラスメント教育のコンテンツを取り扱っています。
新人研修(ビジネスマナーなど)
次にビジネスマナーをはじめとした新人研修にもeラーニングは適しています。
コンプライアンスやハラスメントと同様、基本的なビジネスマナーは内容が決まっています。eラーニングによる学習は、実施や準備の負担を減らすこともできて最適です。
また新人研修は身に付けさせるべき内容が多いため、どうしてもインプット形式でボリュームが大きくなりがちです。eラーニングは各自が自分に必要なところを集中的に復習できるため、学習効果を高めやすいといえます。
特に若い世代はデジタルデバイスへの抵抗もありません。対象者の世代を考えると、eラーニングの活用が効果的です。
イー・コミュニケーションズの eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」では、新人研修向けのコンテンツを取り扱っています。
階層別研修(中堅社員・管理職)
中堅社員・管理職など階層別の研修もeラーニングが役立ちます。中堅以上の社員は、業務が忙しくなるのが一般的です。
そのため集合研修はスケジュールの調整が難しかったり業務の時間を圧迫してしまったりします。すき間時間に学習可能なeラーニングは、そのようなデメリットなしに学習することが可能です。
また階層が上がるにつれ、知識習得だけでなくディスカッションなどを通して考える機会も必要となります。知識はeラーニング、思考はリアル研修など学習内容に合わせた研修方法の使い分けも可能です。
イー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」では、マネージャー向けのコンテンツを取り扱っています。
ビジョン研修(企業理念・会社方針など)
企業理念や会社方針についても、eラーニングによる学習が効果的です。理念や方針は企業の根幹にある考え方ですので、一度教材化すれば繰り返し使用することができます。
さらに理念や方針は企業活動を決める思想的な背景であり、抽象的な内容を多く扱います。そのため、理解・浸透するまで継続的に学ぶ必要があります。理解のための入社時の教育にも、定着のための定期的な確認にも、反復学習に強いeラーニングが役立つでしょう。
専門知識に関する研修
業務上必要な専門知識の習得にもeラーニングは役立ちます。
特に事務系の業務で身に付けるべき知識は言葉で伝えやすい内容が多いため、eラーニングの教材化がしやすく独習が可能です。
語学研修
語学研修もeラーニングを活用することが可能です。英語はもちろんですが、英語以外の、リアルだと学べる場所を探すのが少し大変な言語でも、eラーニングなら比較的簡単に学習できます。自社のビジネスに関わる国の言葉のコンテンツも探せば見つかるかもしれません。
語学の「話す力」はeラーニングだけだと習得が難しい部分もありますが、最近はAIを活用して会話力も伸ばせるコンテンツも登場しています。あるいは「話す」はリアルでの学習、「聞く」「読む」「書く」をeラーニングなどの使い分けも効果的でしょう。
接客・クレーム対応など
店舗での接客やクレーム対応、工場などでの作業も、動画を使った教材であれば独習が可能です。
近年はそういった経験学習型・体験学習型のコンテンツも増えつつあります。
基本的なことをeラーニングで学ばせて、OJTなどリアルの研修でより具体的なコツやノウハウをレクチャーする方法もあります。リアルだけで習得させるよりも効率の良い方法といえるでしょう。さらにオンラインだけでも習得できるよう、学習者が作業の動画を録画して確認してもらうというやり方もあります。
eラーニング研修の導入前に考えるべきこと

eラーニング研修導入前には、次の2点について検討・整理しておきましょう。導入がスムーズになり実際の運用もより効果的に行うことができます。
①研修全体のゴールと設計
②eラーニング研修で行いたい内容・条件
それぞれについて具体的にみていきましょう。
①研修全体のゴールと設計
まず研修全体のゴールを明確にする必要があります。
このとき、主に考えるべき点は次の3つです。
- 対象者と研修内容
- すでに行っている研修の問題点
- 研修の方法
研修の対象となるメンバーによってゴールは異なります。研修内容・範囲と期間を確認し、研修全体で何を、どこまで身に付けさせるのかを明確にしましょう。
例えば、「新入社員向けに企業理念を身に付けさせる」「管理職にハラスメント防止策を理解させる」など対象者に合わせてゴールを決めます。
②eラーニングで行いたい内容・条件
全体像を決めたら、eラーニングだけで完結させるのか、ほかの方法と組み合わせるのかを検討します。組み合わせる場合は、「どの内容をどの方法で学習させるのか」の割り振りを検討することが重要です。eラーニングと組み合わせるほかの方法の例としては、集団研修・グループワーク・OJT・テストなどがあります。
それぞれの特性を踏まえて、内容に応じて最適な方法を当てはめていきます。例えば実技を伴う内容はOJT、知識のインプットはeラーニングといった具合です。
eラーニングで学ばせる内容が決まったら、eラーニング内のゴール(何を、どこまで身に付けさせるか)も明確にしましょう。はじめにイメージした大まかな全体像を、より具体的にしていく作業です。
この際、大まかな予算の割り振りもイメージしておくと後々スムーズに進みます。もちろん具体的な検討段階で修正はあり得るので、詳細を決める必要はありません。
eラーニング研修を導入する4つのステップ

実際にeラーニングを導入する場合は、次の流れで進めると効率的です。
ステップ1.内容・対象・時期・担当者を決定
ステップ2.システム検討・導入
ステップ3.実施
ステップ4.フォローアップ
各ステップについて、具体的にみていきましょう。
ステップ1 内容・対象・時期・担当者を決定
前項で決定したeラーニングで学ばせたい内容に合わせて、教材・形式、対象者、時期、担当者を決定します。
「教材」は、自社で作成したコンテンツを使用する場合と、既存コンテンツを使用する場合があります。
また、「形式」は文字ベースの資料、動画など種類が豊富です。研修内容に合わせて選ぶと良いでしょう。
「対象者」は対象の属性や人数などです。属性の例としては、「新入社員」「入社3年目」「課長以上」「営業職」など、勤務年数・役職・職種などが考えられます。「入社2年未満の店長」のような、属性を組み合わせる場合もありえます。
「時期」は、実務に悪影響が出ないタイミングや実務に役立つタイミングが好ましいでしょう。例えば新製品についての知識なら発売前に知っておく必要があります。スキルアップ研修やリーダー研修であれば、繁忙期を外して行うことがおすすめです。システム導入にかかる時間も考慮して決めましょう。
「担当者」の業務は、システム担当者との連携や不具合への対応のほか、教材の配信や学習者の管理やフォローなども含みます。内容別に分担したり1人が対応したりと、規模や内容によって適した形で決めましょう。
ステップ2 システム検討・導入
次に研修の内容・規模などの条件をもとに、導入するシステムの候補を挙げます。内容(とくに自社コンテンツか提供コンテンツか)や運用の利便性、妥協できない条件と価格のバランスで最終的な判断を行いましょう。
決定後は教材を準備します。システムが提供している既存コンテンツを利用する場合は、どのコンテンツを使うかを選択します。自社で作成する場合は、作成担当者・作成方法・作成の期限なども確認・決定しておかなければなりません。
ステップ3 実施
教材の配信を行い、研修を実施します。
実施中は、受講状況の確認や必要に応じてリマインドやアラートも行います。対象者の抽出がしやすいシステムなら担当者の負担を軽減できます。
そのほか、不具合や質問への対応も行いましょう。必要に応じて他部署や外部と連携することも重要です。
ステップ4 フォローアップ
研修が終了したら、運用に関する振り返りと学習者の成績に関する確認を行います。
運用については、アンケートや全体の成績の集計を行ったりして、改善点の洗い出しと改善方法の立案などを行います。
学習者に対しては、成績がよくなかったメンバーへのフォローや復習を促す連絡などをします。合否を決定するような研修であれば、再試験を実施する場合もあるでしょう。その段取りや連絡も行います。
eラーニング研修を成功させるためのポイント

eラーニング研修を成功させるポイントとして次の2点が挙げられます。
①受講者の進捗管理、サポートを行う
②受講状況・テスト結果に応じでフォローアップする
それぞれ具体的に見ていきましょう。
受講者の進捗管理、サポートを行う
eラーニング研修を成功させるためには、受講者の進捗管理とサポートが欠かせません。定期的に進捗状況や課題提出状況を確認しましょう。
また、受講者が疑問や課題に直面した場合、迅速かつ効果的にサポートできる仕組みを整えましょう。チャット、電子メールなどのコミュニケーション手段を提供し、質問や疑問点の返答をできるだけ速やかに行うことで、受講者の不安を解消でき、モチベーションを維持することができます。
定期的に専門家や、主催者側からのフィードバックを行うことも効果的です。
受講状況・テスト結果に応じてフォローアップする
受講者の受講状況やテスト結果に応じてフォローアップをしましょう。
進捗状況やテスト結果を詳細に分析する機能があるeラーニングシステムを選べば、受講者の苦手な分野を特定することができ、再度受講させるなどの対応が可能です。各自が抱える課題の克服に役立ちます。
ラーニング研修の導入事例

最後に、当社のeラーニングを導入いただいた企業様の事例について簡単にご紹介します。
事例1.不動産系企業様
不動産系企業様のコンプライアンス教育として個人情報保護に関する教育の一環として、当社のサービスを導入していただきました。年に1回、地域・役職別に集合教育を行っていましたが、eラーニングを導入。拘束時間の改善・コストダウン・社員の負担軽減に役立てていただいております。
事例2.IT系企業様
機密情報の管理や法令の理解、また自社の理念や方針の浸透のためにご利用いただいています。操作性とコストから当社のサービスを選択。全社利用と部門ごとの利用の両面で利用していただき、社員の実施率も高く運用していただいています。
事例3.マーケティング系企業様
ビジネスマナーや社会人としてのマインドセットのための新人教育として、内定者・新入社員向けコンテンツを導入いただいております。入社前から変化を感じられるほどで、入社後の現場からのクレームもないとのお話です。
eラーニングシステム「SAKU-SAKU Testing」は、ほかにも多くの企業様で導入していただいています。
eラーニング研修にはSAKU-SAKU Testingをご活用ください
eラーニング研修は、対面研修など、ほかの研修方法と組み合わせてそれぞれの利点を活かすことで、効果的な研修を設計することができます。
eラーニングの導入をお考えであれば、ぜひ「SAKU-SAKU Testing」をご検討ください。
進捗状況や受講状況を確認できるため、受講者一人ひとりの苦手な分野を確認でき、フォローアップすることができます。
また、知識の定着にテストを用いる「テストエデュケーション」による高い学習効果も期待できます。
サクテスは、教育担当者様の声を反映したUIデザインで、誰でも簡単に直感で操作することが可能です。研修を主催する側・受講者側、いずれも効率的に利用できます。
また、ビジネスの場で活用できるマイクロeラーニングコンテンツを多数ご用意。最低限押さえておきたいハラスメントや情報セキュリティ教育から、内定者向け、管理職向けのコンテンツなど、幅広く取り揃えています。
コンテンツ・システム・運用すべてをサポート、さらに、ご希望の場合は代行も承ります。
ご不明の点がある場合やご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。